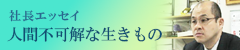人間 ― 不可解な生きもの
田園交響曲
べートーベンの交響曲は九曲ある。これらについてどれが優れているかという議論はあまり意味がない。勿論第九番は深淵であり偉大な曲である。彼の生涯の総決算的な要素を持つ。
どれが好きかというのはその時の心境である。私は第六番いわゆる「田園交響曲」が好きだ。好きというのは漠然的な感性、理屈ぬきに好き、こよなく好きとかいうレベルに分類できる。私のは最初のものであるが、こよなくという要素も含んでいる。
この稿を書くにあたってロマン・ロランの「苦悩の英雄ベートーベンの生涯」を読みかえした。田園交響曲に関する記述があった。よく知られていることだが、彼は20才台の終わり頃、交響曲でいうなら一番を完成させる頃には難聴が強く兆していたので六番の作曲時(三十七才位)には甚だしい状態であった。作家によるとこの田園を作曲することにより自分のなかに小川のせせらぎ等をよみがえらせたという。人に聞かせるというより自分の為に書いたのだという。あの印象的なカッコウのような描写も鳥の声をよみがえらせ、郊外の径(こみち)を歩いているすがすがしい気分を脳内に興すためだという。
あらためてなるほどと思った。彼の肢体は正常なので(強い頭痛は時に彼を苦しめたが)、歩くことはたやすい。静かな田園や森の中で、風の音・木の葉のざわめき・鳥のさえずりはサムシィングをもたらす。それらを感じずんば、歩く意味は殆どなかろう。しかし彼は難聴状態のなかで次々と傑作を生みだし、作曲技法にも独自の進化を遂げさせていった。まさに驚異の人である。ちなみに難聴の作曲家はチェコの(交響詩わが祖国で有名な)スメタナがいる。「楽聖」とベートーベンは呼ばれるが異論を唱える識者は居るまい。
田園は五楽章あり(大部分の交響曲は四楽章だが)各々に標題がついている。一応記すと=一楽章:田舎へ着いたときの愉しい感情のめざめ、二楽章:小川のほとりの情景、三楽章:田舎の人達との楽しいつどい、四楽章:雷雨・嵐、五楽章:牧人の歌―嵐のあとの喜びと感謝の気持ち、である。
その中で私はどこが最も好きかというと嵐の去ったあとに戻ってきたやすらぎと悦びを感じる5楽章である。相当前の私事で恐縮だが2006年12月にザールブリュッケン放送交響楽団、スクロヴァチェフスキ指揮(当時読売日本交響楽団の桂冠名誉指揮者・1923年生れ現在物故)の演奏は最高だった。その五楽章はなぜか涙がでてきたものだった。
驚異の人と前述したが、個人的な性格は極めて真っ直ぐであったと想像される。時に真っ直ぐ過ぎて普通の人からは逆にネジれているようにも思われたかもしれない。つる植物がうまく曲がったりネジれたりして生長してゆくように人間は状況に合わせて適当に生きているわけだが、彼はそれがうまくできなかったのではと私は思う。結果他人からすると不可解な言動・行動が多かったに違いない。自信家であった彼は時に尊大・失礼な奴と見られていたようだ。また思うに意志の強靭さは尋常でないものがある。そうでなくば極度の難聴状態(かすかには聞こえた)で「傑作の森」といわれる作品群を創りあげることなどできなかったに違いない。加えて彼の音楽の真骨頂は「劇性」にある。私のレベルではうまく説明できないがグイグイくる推進力に裏付けされた劇(的)性(ヒロイック・トラジック・熱狂性・純粋性―天上的なまでの)を感じてならない。
現一般社会ではベートーベンよりモーツアルトの方が多分人気が高いが、モーツアルトはしばし似た感じを持つ曲が多い。ベートーベンは確かにこれはベートーベンだと思わせる一方、メロディラインは同人の曲の間では似たものが極めて少ない。交響曲のみに関しては、全九曲三十八楽章あるが、みんなまるで違う。くどいようだが彼は人類史上、不思議なまでに奇跡の人と言わざるをえない。