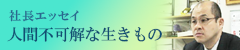人間 ― 不可解な生きもの
プロテスタントってどうゆうもの?(その一)
数年ほど前にキリスト教にあらためて興味をもち、買い求めた関連本に東洋英和学院校長(当時)深井智朗氏の「プロテスタンティズム・中公新書」があった。読売新聞の本人手記を見て興味を持ち購読したところ、なるほどもっと早く知ればよかったと強く思う記述が多々あった。
同著は修道士で大学教員であったマルティン・ルターがローマ教皇庁に対する九十五か条の提題文を当時普及しはじめた活版印刷を使いドイツ・ヴィッテンベルグの町より三百通ほど発信した一五一七年の五百年後を期して著したもので、吉野作造賞を受賞した。ルターの同文の代表条項は免罪符(現在は贖宥状という)の濫発に対しての詰問的な問題提起である。その他細々書き立て九十五か条に及ぶ起案より一連の行動へ注がれたエネルギーは、生命の危険を生ずるなか、尋常でない決意と勇気を伴うものであった。
キリスト教の会派は大雑把にカソリック・正教・プロテスタントに分かれる。もちろん当時は前二者しかないが、当時のキリスト教社会の人々には現代日本人からは想像不能なほど地獄堕ちへの恐怖感が植え付けられていたようだ。贖宥状は当然金銭授受にて発行される(半オーダーメード的らしい)もので、集まった膨大な資金の流末はローマ、ヴァチカン・サンピエトロ大聖堂の建設費に充てられた事はよく知られている。贖宥状を得ることにより地獄に堕ちる(懸念のある)人は中間地点の煉獄へ、煉獄の人は天国へ行くことに嵩上げされる。
ちなみに教会からの破門は相当な恐怖であるらしく、破門された人は闇で葬られても司法は見て見ぬふりをするらしい。破門がらみの有名な出来事は「カノッサの屈辱」がある。一〇七七年に神聖ローマ帝国皇帝のハインリッヒ四世が、時の法皇グレゴリウス七世に破門され、復権を得たいが為に裸足で三日間門前に立ち凍傷になったという事件だ。つまり破門により皇帝の権威が極端に失墜し、地位の回復の為にそこまでせざるを得なかったということを意味する。
斯くのごとくカソリックの頂点は当然ローマ法皇である。その基にあまたの大司教・司教及び枢機卿らがいる。なかでも大司教は大司教区という領有地をもっていて(その地位は必ずしも世襲ではない)絶大であるという。ルターの時代のマインツ大司教アルブレヒト・フォン・ブランデンブルグは一人一司教区の原則を破り二大司教区の地位を狙い、達成のためにローマ教皇庁宛てにサンピエトロ大聖堂建設費への破格な負担を重ねた。その資金はドイツ・アウグスブルグの金融・鉱山業を営むフッガー家より借り受けた。よってその返済に充てる為、贖宥状の発行を主に神聖ローマ帝国内(現代のドイツ・オーストリアを概ねとする地域)にてしげくしたという。何故そんなに売れたかは天国への道筋は教会といういわば「専属旅行代理店」を経由しないと絶対にゆけない恐怖心を人々の心へ植え付けた成功にあるという。また聖書の解釈は法皇を頂点とした教会の権威がすることで、一般人が勝手に考えるものではないというのが当時の根本という。
ルターはそれについてまず疑問を呈した。当時のドイツ語版新約聖書は不完全で(原初はヘブライ語やギリシャ語だがラテン語版が正規に原文とされていた)、民衆は聖職者の説法を聞くことにより断片的に知っていった(教会のステンドグラスは聖書関連の名場面集だ)。そしてルターはそのような次第で教会の都合による諸学説に民衆が惑わされている現状を脱却すべく、新約聖書に書いてあることこそが絶対的と捉えたが、その解釈については個人差があってしかるべきとの新構想をうちたてた。よってそれにより自我が萌芽え、ヨーロッパ社会を中心に自我~個人が確立していったとの説が強い。